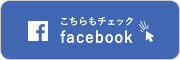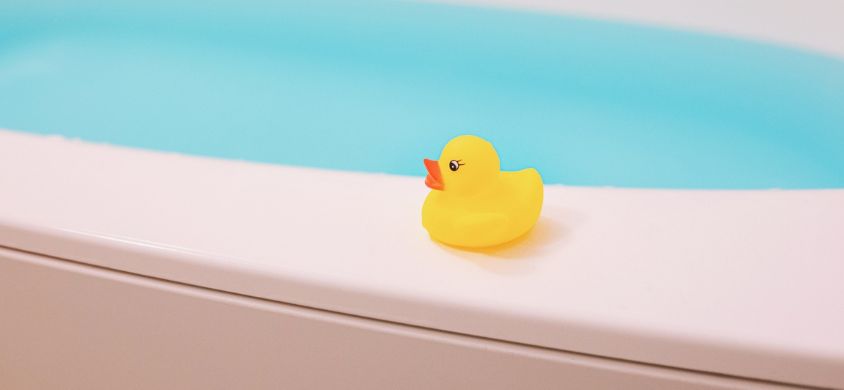お風呂をピカピカにするための大掃除完全ガイド
毎日使うお風呂は、1年間の汚れが溜まりがち……。
年末の大掃除で、気持ちよく新年を迎えたいものです。
ただ「お風呂の掃除方法を調べてもいろんな方法があってよく分からない」「ちょっとハードルが高いかも」とお悩みの方はいらっしゃいませんか?
今回はお風呂掃除完全ガイドと称して、お風呂掃除のいろはを徹底解説しちゃいます!
また、ビッグバイオではお風呂の防カビに特化した商品を販売しています。
お風呂掃除で用意するべき基本の掃除道具

- スポンジ(ハンディタイプがおすすめ)
- 床用ブラシ(あればお掃除がラクに)
- 部分用ブラシ(歯ブラシなど先の小さなもの)
- ゴム手袋・マスク
- お風呂場用の靴
- 洗剤
基本は上記の道具で良いですが、キッチンペーパーやラップがあると黒カビ除去などに役立ちます。
しっかりと浴槽を洗いたい場合は、スポンジはハンディタイプがおすすめです。
柄のついたタイプよりもハンディタイプの方が力を入れやすく、汚れをピンポイントに落とすことができます。
絞りやすいため、乾きやすいのもハンディタイプのメリットと言えるでしょう。
上記の中でも特にお風呂場のカビ掃除の際は手袋とマスクは必須と考えましょう。
カビの胞子を吸い込んだり、洗剤が目に入ったりするリスクを回避するためです。
洗剤の選び方について

お風呂掃除、または年末の大掃除に必要な道具はお風呂場の汚れ具合によります。
- 赤カビ(ピンクヌメリ)
- 黒カビ
- 石鹸かす
- 水垢
- 皮脂汚れ
上記はお風呂場の主な汚れですが、種類によって準備した方が良い洗剤の種類は異なるため、事前に確認しておきましょう!
また、汚れの種類だけでなく汚れが付着している素材によっても洗剤を使い分ける必要があります。
石鹸かすや皮脂汚れは黒カビの原因。
これらの汚れを放置していると、厄介な黒カビの発生につながってしまう恐れがあります。
石鹸かすなどは比較的簡単に落とすことができますが、黒カビはそうもいきません。
黒カビが発生してしまう前に、定期的な掃除を行うことできれいな浴室を保つようにしましょう。
中性洗剤
中性洗剤は普段のお手入れやお風呂全体に使えるため、1つは常備しておきましょう。
ただ、頑固な汚れの場合、中性洗剤では対応できないことがあります。
中性洗剤で落としきれない頑固な汚れは、それぞれに適した洗剤を使用しましょう。
アルカリ性の汚れには酸性洗剤。
逆に、酸性の汚れにはアルカリ性洗剤が適しています。
水垢や石鹸カスには酸性洗剤

アルカリ性の汚れには酸性の洗剤を使いましょう。
アルカリ性の汚れとは、水垢や石鹸かすなどのこと。
白く固まることが多いのが特徴です。
カビや皮脂汚れにはアルカリ性洗剤
酸性の汚れにはアルカリ性の洗剤を使いましょう。
酸性の汚れには黒カビや赤カビ、皮脂汚れがあてはまります。

お風呂場だけでなく台所なども同様で、例えばキッチンの油汚れも酸性の汚れに該当するため、アルカリ性の洗剤を使用すると良いでしょう。
酸性の汚れはアルカリ性の汚れと比べてぬるぬるしていることが特徴です。
また、塩素系漂白剤は強いアルカリ性のため、黒カビ除去におすすめ。
洗剤以外に掃除で使用するもの
洗剤以外におすすめなのが「重曹(アルカリ性)」と「クエン酸(酸性)」です。
どちらも人体に無害なため、小さな子どものいる家庭でも安心して使用することができます。
洗剤を使用する際の注意点
アルカリ性洗剤と酸性洗剤の併用は、絶対にしないでください!
混ざってしまうと、人体に有毒なガスが発生して非常に危険です。
どちらかの洗剤を使ったあとは、流し残しがないように注意しましょう。
関連記事:掃除してもお風呂がカビ臭いのはなぜ?根本原因や掃除方法について解説
素材との相性について

汚れの種類によって洗剤を使い分けるとお話しましたが、それ以外にも汚れが付着している素材によっても洗剤を使い分ける必要があるため注意が必要です。
例えば、ホーロー製の浴槽の場合アルカリ性洗剤や塩素系漂白剤の使用は避けた方が良いとされています。
ホーローの表面のツヤを損ない、劣化を早めてしまう可能性が高いためです。
または、材質によっては洗剤を直接スプレーするとシミになることがあります。
こうしたトラブルを防ぐためにも、使用したことのない洗剤を使用する前に下記の方法を試しましょう。
- 液性が弱い(中性)ものから順に試す
- スポンジに含ませて様子を見ながら洗う
- 傷つきやすい硬いブラシは使わない
また、注意したい素材例を下記にあげています。
ポリ製の浴槽
酸性洗剤やアルカリ洗剤で変色するため、中性洗剤がおすすめ。
ステンレス製の浴槽
傷がつきやすいため、目の粗いたわしやクリームクレンザーなどの使用は避けましょう。
傷がつくと光沢がなくなったり、かえって汚れが落ちにくくなったりするデメリットも生じます。
効率的なお風呂掃除の手順

お風呂掃除を始める際、まずは換気することを忘れないようにしましょう!
換気扇は必ずつけるようにして、窓があれば開けておきます。
特に塩素系漂白剤には独特な刺激臭があるため、換気は必須!
基本的には中性洗剤の使用である程度の汚れは落ちますが、頑固な汚れにはそれぞれに適した洗剤を使用しましょう。
大まかな掃除の手順としては、
- 皮脂汚れを落とす
- カビを除去する
- 石鹸かすや水垢を落とす
です。
皮脂汚れがついたままカビ取りをしてしまうと、殺菌効果が弱まってしまいます。
最初に必ず、皮脂汚れを落とすのが効率的なお風呂掃除のコツです!

お湯で洗い流したあと、塩素系漂白剤などのカビ取り洗剤を吹きかけます。
5〜10分程度放置して、カビに洗剤を浸透させましょう。
この際キッチンペーパーかラップを被せることでさらに高い効果が期待できます。
時間が経ったらスポンジでカビ汚れを軽く擦って落としていきます。
強く擦ると細かい傷がつき、そこからカビが発生しやすくなってしまいます。
ハイターなどのカビ取り洗剤は強力な薬剤が使われているため、必ずゴム手袋やマスク、保護メガネをしてくださいね。

カビ取り剤を水でしっかりと流したら、酸性洗剤を用いて石鹸かすや水垢を落とします。
カビが生えていないようであれば、皮脂汚れや水垢の掃除だけでも十分でしょう。
この基本の流れを覚えたら、さっそくお掃除本番です!
とはいったものの、上記の流れを守ればお風呂場のどこからでも洗って良いわけではありません。
おすすめの洗う順番は……。
洗う順番は「上から下へ」!

お風呂場の掃除をする際は、上(天井)から下(床)に向かうのが基本です。
水は上から下へ流れるため、床を掃除したあとに天井を掃除してしまうと、せっかくきれいにした床が再び汚れてしまいます。
大まかな順番で言うと
- 天井
- 壁、扉、窓
- シャワーヘッド、蛇口、鏡
- 浴槽
- 床
- 排水口
です。
基本的には天井の汚れ(皮脂→カビ→水垢の順番)を落とし、次に壁の汚れ……となります。
掃除を始める前に、目に見える髪の毛などは取っておきましょう。
具体的な掃除方法について解説しますね。
天井
天井は湿気が溜まりやすく、気づいた頃にはカビが生えていた……なんてことが多い場所です。
天井の掃除には、フローリングワイパーがおすすめです。

そう、リビングなどの掃除に使う「あれ」です!
キッチンペーパーなどに洗剤を吹きつけて、ワイパーにセットすれば準備は完了。
そのまま天井へ押しつけるように、ゴシゴシするだけでOK!
カビが発生している場合も同様です。
キッチンペーパーにカビ取り洗剤を吹きつけて、ワイパーにセットしたあと天井を擦りましょう。
もし、中性洗剤を使ったあとでカビ取り洗剤を使用する場合、洗剤が混ざらないよう、必ずきれいに洗い流してから使用してください!
カビ取り洗剤とそれ以外の洗剤が混ざってしまうと、人体に有毒なガスが発生して非常に危険です。
壁、扉、窓
天井のあとは壁や扉、窓を洗います。
汚れがひどくなければ中性洗剤をつけたスポンジで擦るだけで良いでしょう。
扉や窓のサッシ部分にカビが生えている場合は、塩素系漂白剤などを吹きかけ、キッチンペーパーかラップを被せて数分間放置します。
そのあと擦り洗いをしてよく洗い流しましょう。
シャワーヘッド、蛇口、鏡

シャワーヘッド、蛇口、鏡は特に水垢が発生しやすいところです。
基本的には中性洗剤で落とすことが可能ですが、頑固な場合は酸性の洗剤やクエン酸の使用をおすすめします。
また、シャワーヘッドは水垢だけでなくカビが生えやすい場所でもあります。
もしシャワーヘッドのカビが気になる場合は、中性洗剤を混ぜたお湯にしばらく浸しておきましょう。
そのあと、歯ブラシなど先の小さなブラシで重点的に掃除してください。
浴槽
浴槽は中性洗剤とスポンジを使います。
基本の汚れは中性洗剤とスポンジで良いのですが、壁との接地部分にあるカビには塩素系漂白剤で対応しましょう。
壁と同様、カビが気になるところに洗剤を吹きかけてラップやキッチンペーパーを被せ、数分後に擦り洗い、流します。
床
あまり汚れていないようであれば、中性洗剤とスポンジで十分です。
ピンポイントで擦ることのできる歯ブラシなども準備しておくと良いですね。
排水口
排水口の掃除はヘアキャッチャー(目皿)や排水口カバーの髪の毛やごみを取り除くことから始めます。
ヘアキャッチャーを外して、水の溜まった筒状のパーツがあればそれも外しておきましょう。
この際、パッキンも忘れず外しておきます。
パーツを外したら、排水口の入口を中性洗剤とスポンジで洗いましょう。
入口付近の汚れはほとんどが髪の毛や皮脂など。中性洗剤で十分です。
シャンプー容器なども要チェック
お風呂掃除の際はシャンプー容器やいすなどの小物も確認するようにしましょう。
シャンプー容器をタイルなどに直接置いている場合、ぬめりが発生していることがあります。
掃除を怠ってしまいがちな箇所ですが、ここから黒カビの発生につながることがあるため、しっかりときれいにしておきましょう。
きれいなお風呂で新年を迎えましょう

お風呂をピカピカにすることは、単に汚れを落とすだけでなく、心身のリフレッシュにつながる大切な時間です。
今回の記事を参考に、ぜひあなたも、清潔で気持ちの良いお風呂で新年を迎えてくださいね。
より快適なバスタイムを送りたい方へ。
当社の「with BIO お風呂の防カビ 貼るタイプ」は、天然成分100%で作られた、人体に優しい防カビ剤です!
3カ月間効果が持続するので、面倒なお掃除の手間を省くことができます。
環境にも人にも優しい、新しいお風呂掃除の習慣を始めてみませんか?