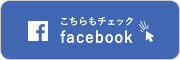微生物の未来 〜 その14:発酵の未来は、もっと自由で、もっとサステナブル。 微生物がつくる新しい“食”の世界へ 〜
こんにちは、tsuです。
気づけば、もう年末を迎えようとしています!!
皆さんにとって、どんな一年だったでしょうか?
この時期に、今年の振り返りをしておくと、
来年に向けてつながるかもしれません。
1 はじめに
さて、前回、未来を変える小さな生き物たちということで、微生物の活用方法を紹介させていただきました。
私たちの食卓には、昔から多くの「微生物のしごと」が並んでいます。
納豆、ヨーグルト、味噌、醤油、チーズ、キムチ…。
これらは、微生物が原料を変化させ、うま味・香り・栄養価を高める“発酵”によって生まれた食品です。
しかし、微生物がつくる食の世界は、今まさに大きな転換期にあります。
伝統的な発酵食品だけでなく、人工的にデザインされた「新発酵食品」 や、
微生物が直接たんぱく質を生産する“発酵ファーム” の実現、
さらには、家庭・地域で楽しむDIY発酵文化 など、食の未来に向けて新たな潮流が広がっています。
今回は、その最前線をわかりやすく紹介します。
2 発酵食品 vs 新発酵食品
伝統発酵から、人工発酵・合成食品へ
発酵食品の歴史は長く、人間と微生物の共同作業ともいえる文化を築いてきました。
伝統発酵の主役は、乳酸菌、酵母、麹菌など、自然界に存在する微生物たちです。
一方、近年注目されているのが 「新発酵」 と呼ばれる分野です。
● 酵母や細菌の代謝経路をデザインし、
・チーズの香り成分だけを作る微生物
・ココアやバニラの風味を作る微生物
・動物性成分を使わず「ミルクタンパク質」を合成する微生物
など、合成生物学(Synthetic Biology) の力を使って、目的の食品成分をつくる技術が急速に発展しています。
これにより、
動物性食品に頼らない持続可能な食の生産
アレルギーを持つ人のための代替食品
味・香り・栄養を自由に設計した“未来の食品”
といった新たな選択肢が広がっています。
3 将来の”発酵ファーム”
微生物がつくるたんぱく源:SCP(単細胞たんぱく質)
世界的に、たんぱく質危機(プロテインクライシス)が叫ばれています。
人口増加に対して、畜産・漁業だけでは供給が追いつかないことが予測されるためです。
そこで注目されているのが、微生物自身を“食べる”という発想。
これが SCP(Single Cell Protein:単細胞たんぱく質) です。
・酵母
・藻類
・細菌(例:メタンを食べて増える微生物)
これらを大規模タンクで培養し、乾燥して食品原料とします。
すでにフィンランドやアメリカでは、微生物タンパク質を使った肉代替食品が登場し始めています。
微生物は、少ない水、少ない土地、短い時間で高栄養のたんぱく質を生み出す“未来の工場” です。
将来的には、都市部にも設置できる「発酵ファーム」として、食料自給の一助になる可能性があります。
4 消費者参加型の発酵文化
家庭用キット、DIY発酵、地域発酵コミュニティ
発酵は、実はとても“身近に実践できる科学”です。
最近では、消費者や地域が主体となって発酵文化を発展させる動きも増えています。
● 家庭で楽しむDIY発酵
手作りヨーグルト
自家製味噌
発酵ドリンク(コンブチャ、乳酸発酵ジュース)
パン用天然酵母のおこし方
SNSでは発酵レシピが共有され、「菌を育てる」こと自体が楽しみになっています。
● 発酵コミュニティの形成
地域の味噌蔵や発酵食品店がワークショップを開いたり、
地域の独自発酵文化を観光コンテンツ化する動きも見られます。
“土地ごとの微生物”が作る味わいは唯一無二で、
これは 「テロワール(土地性)」ならぬ「マイクロバイオーム・テロワール」 とも言われます。
微生物が、地域文化を支え、コミュニティをつなぐ存在になりつつあるのです。
5 微生物が広げる、新しい食の未来へ
伝統的な発酵食品はこれからも愛され続けます。
その一方で、デザインされた新発酵食品
微生物が生産する代替タンパク質
消費者参加型のDIY発酵文化
といった多彩な流れが共存し、微生物と食の関係はこれまで以上に豊かになっていきます。
「微生物は、未来の食をつくるパートナー」
そう言っても過言ではないのかもしれません。